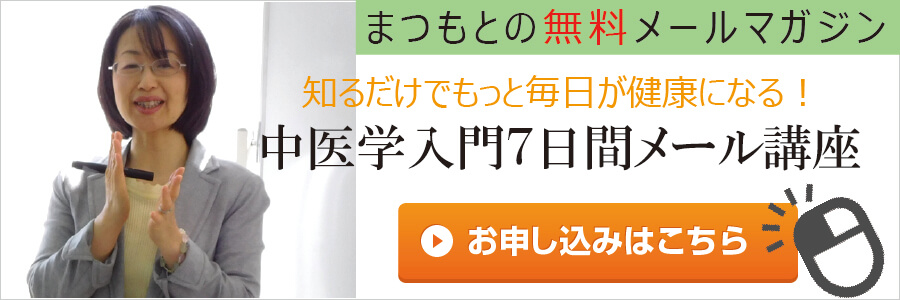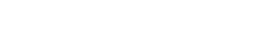皮膚のお悩み
女性のお悩み
メンタルのお悩み
アレルギーのお悩み
胃腸のお悩み
泌尿器のお悩み
全身のお悩み
耳鼻のお悩み
皮膚のお悩み

アトピーとはどういう病気か
「ジュクジュク・アトピー」を漢方&養生で治す方法
「カサカサ・アトピー」を漢方&養生で治す方法
「掌蹠膿疱症とは」
×
女性のお悩み

女性は、勉強・お仕事・家事や育児などいろんな場面でストレスを受ける機会が多く、自律神経の調子が乱れがちです。それに伴い、生理不順、生理痛、PMSなど、女性の月経にまつわるお悩みも増えています。
わたしたちまつもと漢方堂では、中医学に基づいて女性の健康回復をお手伝いしています。「女性だから」「年齢だから」と諦めないでご相談ください。
以下にはよくみられる女性のお悩みと、その対処法を紹介しています。こちらに挙げていないお悩みも、諦めないでご相談ください。

生理不順
西洋医学では、通常の月経は、生理周期が25~38日間、生理期間が5~7日間とされています。女性ホルモンが乱れることにより、生理が来たり来なかったり、生理周期がズレる、出血期間が一定しないといった症状が生理不順と呼ばれます。生理痛を伴うこともあります。
中医学では、28日を基準として生理周期がそれより7日以上早まる、7日以上遅れる、あるいは安定しない、といったことが2~3回以上続くと、生理不順であると考えています。生理不順は「肝」や「腎」の機能低下と深く関わっており、そのうえに、「気血不足」、流れが滞って古くなった血、冷え、余分な老廃物が煮詰まっている状態などが複雑に絡み合って、生理不順を引き起こすと考えています。
そこで対処法としては、「肝」の気の巡りをよくし、「腎」の働きを整えることを中心とします。それに加え、その方に必要なお手当を加えて体調を調整し、「健康な生理」に近づけていきます。
生理不順-1
【ダイエットで生理が来なくなった・24歳女性の改善例】
Aさんが漢方相談にお越しになったのは2020年の4月。やせ型で、年齢の割にお肌の乾燥が目立つ、元気のなさそうなお嬢さんでした。
お悩みは「生理不順」。詳しくお話をおうかがいすると、20歳を過ぎた頃からダイエットのため、糖質、脂質制限の食事をなさっていたそう。そのかいあって、体型は望み通りスリムになられたのですが、その後は食べようと思っても食欲が湧かず、食べられる量自体が減ってしまいました。そうしてとうとう、生理があまり来なくなってしまったのです。
今は、生理は順調に来なくなり、3ヶ月から長くて5ヶ月も間隔が空くようになり、生理期間も3~4日。下りてくる経血の色も淡く、いかにも「血が薄い」感じになってしまいました。生理不順のほか、クラクラとめまいがする、身体がだるく疲れた感じで、動悸もするようになっていました。Aさんがおっしゃるには、「仕事の忙しいときに疲れてだるく、動悸もする。困る...本当にツラいんです!」とのこと。
Aさんのお悩みは、中医学的には「脾虚・血虚」と考え、「脾(胃腸の吸収力)の働きを上げて血が増えやすくし、月経を整える」方向性のお手当をしました。選んだ漢方薬は3種類です。
その後、Aさんの症状は順調に回復し、3ヶ月後にはめまいの程度、頻度がかなり下がり、6ヶ月後には生理も順調に来るようになりました(月32000円程度)。ご相談の中でAさんは、ご自身が「もともと丈夫な方でなかった」と気付かれ、体力づくりのために今も漢方薬を続けておられます(月22000円程度)
Aさん「漢方薬を飲んでから生理もめまいも良くなってきて、もっと仕事を頑張ることができました」
まとめ)生理不順を悩む女性・Aさん24歳
使用したお手当=3種類 計約32000/月
6ヶ月で改善・その後体力づくりのため月22000円程度で継続中
※個人が特定されないよう、複数の方の事例を合成して「よくあるご相談例」としてご紹介しています。

PMS(月経前症候群)
西洋医学では、PMSは生理前に生じる体の不調や心の不調を指しています。体の不調としては、お腹が張る、乳房が張る、倦怠感、頭痛、腹痛、腰痛、食欲不振、食欲増進、むくみ、肌荒れなどがみられます。心の不調としては、イライラ、落ち込み、泣きたくなる、怒りっぽい、寝つきが悪い、熟睡できない、日中に眠気、集中できない、ボーっとするなどがみられます。ほとんどは生理の3日から10日前に始まります。
中医学では、PMSは主に肝の気の巡りが滞っていることによって引き起こしたものだと考えています。また、血の滞りや水の停滞、気血不足もPMSを引き起こすこともあります。
肝の気の巡りを良くして、体質、月経のサイクルに合わせて、気血を補い、血や水の流れを促進して、PMSの症状を緩和していきます。
PMS-1
【生理前にイライラが止まらない・29歳女性の改善例】
Bさん(会社員・29歳)が漢方相談に来られたのは2021年8月。やせ型で、真面目そうな、ややせっかちなお嬢さんという印象でした。
詳しくお話をおうかがいすると、就職してから、生理の10日くらい前からとてもイライラし、怒りっぽいのを止められないそう。また、その時期にはお乳が張り、先が衣服に擦れるととても痛いとのこと。イライラするのと同時に、便秘と下痢を繰り返し、市販の便秘薬と整腸剤を飲んでも効果はなかったとおっしゃってました。
睡眠について質問すると、寝付きに時間がかかる、眠っても夢が多くてグッスリ眠った感じがしておられませんでした。そのせいか、めまいと立ちくらみもあり、「心の余裕がないんです」とのこと。
Bさんがおっしゃるには、「胸が張ってイライラするときは仕事に集中できないのが一番ツラいんです!」とのこと。
典型的な「PMS(月経前症候群)」の不調と言えます。Bさんのお悩みは、中医学の考え方では「血の不足のせいで気がスムーズに巡らなくなり、胃腸の消化機能にまで影響を及ぼした(血虚、肝鬱脾虚)」と判断されます。
選んだ漢方薬は3種類です。その後、BさんのPMSは順調に回復し、4ヶ月後にはお乳が張って先が衣服に擦れて痛むこと、便秘と下痢がなくなりました(月32000円)。6ヶ月後にはPMSの症状があまり出なくなり、お仕事にもしっかり集中できるように。ご相談の中でBさんは、「気持ちが晴れやかになって快適です!」などとおっしゃっていました。今も漢方薬を続けておられます(月15000円)。
まとめ)PMSを悩む・Bさん29歳
使用したお手当=3種類 計約32000円/月
6ヶ月で改善、体調維持のため月15000円程度で継続中
※個人が特定されないよう、複数の方の事例を合成して「よくあるご相談例」としてご紹介しています。

生理痛
西洋医学では一般的に、生理中に生じる下腹部の痛みを生理痛と呼びます。経血を排出するため、子宮を収縮させる際に痛みが起こると考えられています。また、子宮筋腫や子宮内膜症も生理痛を引き起こします。
中医学では、生理痛は血の巡りが停滞して生じた瘀血が主な原因であると考えています。また、冷えや気の滞り、気血不足などは複雑に絡み合って、瘀血をひどくし、経血がスムーズに排出できなくなると、生理痛に繋がります。
血の巡りを良くして、体質に合わせて、冷え、気の巡りを改善したり、必要に応じて気血も補って、生理痛を軽減していきます。
生理痛-1
【鎮痛剤がだんだん増えてきた・31歳女性の改善例】
Cさんが漢方相談にお越しになったのは2020年の5月。Cさんは目の下にクマが目立つ、痩せ型であまり元気のない印象……という女性でした。
お悩みは「生理痛」。詳しくお話をおうかがいすると、11歳で初めて生理が来てからずっと生理痛があり、就職してからは鎮痛剤を使わないと仕事へ行けないほどの痛みでしたが、最近鎮痛剤の使用量が増えてきたのだそう。生理が来る度に下腹部の痛み、片頭痛があって、仕事をお休みせざるを得ないことも。
下りてくる血液は紫がかった暗い色で、米粒から黒豆ほどの血の塊が混じります。「生理が来た」と思ってもなかなかスッキリと下りてこず、出血のピークは3日目。痛みのピークも3日目です。
Cさんは、「年々痛みが増すので、この先どうなるのか不安になって」と心配してお越しになったのでした。
Cさんのお悩みは、中医学の考え方では、「体を温める力が弱いことから気血の流れが滞って強い痛みを起こしている」状態でした。そこで、内臓の中でもとくに「脾」と「腎」の働きを上げて体の芯を温められるパワーをつけ、血を増やして気とともに流れをよくするお手当をしました。漢方薬は3種類です。
その後すっかり良くなられ、8ヶ月でお手当終了されました(月32000円程度)。その後は、相談中にご提案した中医養生を続けて、生活されています。
まとめ)生理痛を悩む女性・Cさん31歳
使用したお手当=3種類 計約32000円/月
8ヶ月で改善し、お手当終了
※個人が特定されないよう、複数の方の事例を合成して「よくあるご相談例」としてご紹介しています。
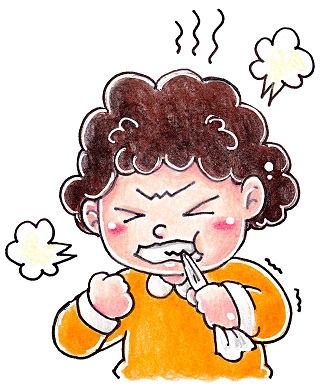
更年期障害
西洋医学では、閉経前の5年間と閉経後の5年間が更年期と呼ばれます。卵巣の活動が次第に減退して月経が来なくなり、閉経に至ります。その前後に現れる日常生活に支障を来すさまざまな心身の不調を更年期障害と言います。
よくみられる症状として、ほてり、のぼせ、ホットフラッシュ、めまい、動悸、頭痛、腰痛、関節痛、冷え、疲れやすい、イライラ、気分の落ち込み、情緒不安定、睡眠障害などがあります。
中医学の考え方では、更年期障害は「腎」の衰えが根本的な原因であり、腎の陰陽バランスが崩れて、「心」や「肝」、「脾」といった他の臓腑にも影響が及び、さまざまな心身の症状が現れると考えています。
中医学では、「腎」を補うことをメインにして、陰陽バランスを整え、「心」や「肝」、「脾」の働きを調整して、不調の出ない身体に整えていきます。すべての症状を取り除くのは難しいこともありますが、まずは日常生活に支障がない程度を目指します。

不妊
西洋医学では、避妊せずに夫婦生活をとって1年以上経っても妊娠に至らない場合を不妊と言います。女性側の原因は、排卵障害や卵管閉塞、子宮筋腫、子宮内膜性、何らかの免疫異常で抗精子抗体を持つなど、見つかることもありますが、とくに問題は見当たらないこともあります。フーナーテストやホルモン検査、子宮卵管造影検査などを行って、結果に応じてタイミング、人工授精、体外受精といった不妊治療を行っています。
中医学では、次世代を生み出す生殖は「腎」の働きであると考えています。この「腎」や「腎」と連携している他の臓腑の働きが低下して「気」「血」「精」が充分にないと、妊娠しづらくなると考えています。
「腎」を補うことをベースに、「腎」と連携して働く他の臓腑の働きを整え、「気」や「血」、「精」などに不足があればそれを補い、妊娠しやすくなる体質に改善していきます。西洋医学の不妊治療と同時進行で行って、よい結果を得る方も多いです。

黄体機能不全
西洋医学では、排卵後、卵を排出した卵胞は「黄体」に変化し、黄体ホルモンを分泌しますが、何らかの原因で黄体ホルモンが弱く、着床しにくく妊娠が成立しにくい状態になっていることを、黄体機能不全を呼びます。黄体機能不全は、黄体ホルモンの分泌量が少ないこと、分泌期間が短いことの両方を含みます。
中医学では、黄体機能不全は腎陽不足が主な原因で、「心」と「肝」の不調や痰湿、瘀血も複雑に絡み合って引き起こされると考えています。
腎陽を強め、血を養ったり「心」や「肝」の働きを整えたり、痰湿や瘀血があればそれを解消したりと、ひとりひとりの状態に合ったお手当を選択します。

高プロラクチン血症
授乳中の母親が妊娠すると、母乳を飲んでいる赤ちゃんの生存率が下がるので、自然妊娠しないように、下垂体から乳汁分泌ホルモン(プロラクチン)が分泌されている間は排卵しません。高いストレスにさらされていると、とくに授乳していなくてもプロラクチンの値が高まり、生理不順や排卵しなくなるといった症状がみられます。これが高プロラクチン血症です。
中医学では、高プロラクチン血症はストレスなどで「肝」の気の巡りが滞って起こると考えています。「肝」の不調を改善することで、排卵がスムーズで生理周期が安定した、妊娠しやすい身体づくりをしていきます。
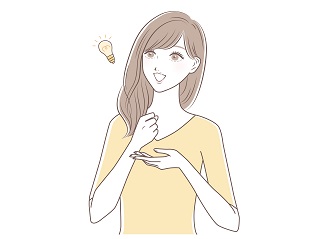
卵巣嚢腫
西洋医学では、卵巣にできる腫瘍のうち、袋状になったものを卵巣嚢腫と呼んでおり、良性なものが多いです。嚢腫の中身は、子宮内膜組織や水様、粘液様の物質が溜まっているもの、毛髪や皮膚の組織が詰まっているものがあります。卵巣嚢腫が小さいうちは自覚症状も少ないですが、大きく育つと痛みや張りが出るひとも多く、腰痛、便秘、頻尿が見られる場合もあります。
中医学では、卵巣嚢腫を形成する主な誘因は瘀血(血の流れが滞って古い血から形成した病理産物)であると考えています。ストレスによって気の巡りが低下すると起こりやすく、余分な水、気血不足なども複雑に絡み合っています。
瘀血を解消すると同時に、瘀血をつくる原因である体質を改善していきます。気の巡りを回復させ、余分な水を代謝し、気血を補い、卵巣嚢腫の成長しにくい体調に整えます。

多嚢胞性卵巣症候群
西洋医学では、多嚢胞性卵巣症候群は、思春期から青年期の女性に排卵障害が見られる疾患です。ホルモンバランスの乱れによって卵胞が育ちにくくなり、なかなか排卵しない、月経周期が35日以上、ニキビが多い、毛深いなどの症状がみられます。育ちきらなかった小さい卵胞がたくさん溜まって、画像診断ではネックレスのような形に見えることもあります。
中医学では、腎の機能低下がベースにあると考えています。余分な水分が溜まったり、気や血の巡りが停滞したり、巡りの滞りによって熱が生じたりすると、腎の機能低下と相まって多嚢胞性卵巣症候群に発展していきます。
改善するには、「腎」を補って機能回復させることをメインにした上で、体質に合わせて、余分な水分を排出させたり、気や血の巡りを良くしたり、不要な熱を取り除いたりと、その方特有のアンバランスを調整することを目指します。

習慣性流産・不育症
西洋医学では、妊娠して22週間未満で流産3回以上繰り返した場合を習慣性流産と言います。22週未満の流産が2回以上、22週以降に死亡した胎児を出産、新生児が生後1週間以内に死亡したことを繰り返した場合を不育症と言います。
中医学では、腎の機能低下、気血不足が習慣性流産及び不育症の根本的な原因であると考えています。そのうえ、胃腸機能低下、瘀血、熱の邪気が体の中に入り込む、余分な水分が温まって煮詰まってしまう、といったことも複雑に絡み合っています。
腎と気血を補うことを重点に置き、体質に合わせて、胃腸の機能を回復させたり、瘀血を解消したり、熱の邪気を追い払ったり、余分な水分を排出したり、体質改善によって元気な赤ちゃんを育てられるような体質をつけることが期待できます。
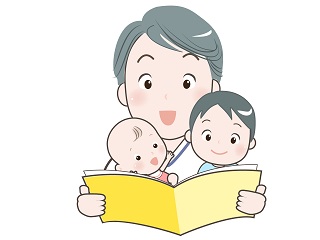
男性不妊
最近の研究では、女性側に原因がある不妊は不妊全体の半分以下で、男性側に原因があるケース、男女双方に原因があるケースが従来思われていたよりも多いことが分かっています。
男性も種々の検査を受け、中医学によるお手当を加えることで、よい結果につながることがあります。諦めずに、ご夫婦ご一緒にご相談ください。

産後に現れるこころとからだの不調
西洋医学では、産後に現れるこころとからだの不調は、出産後の女性に女性ホルモンバランスの変化や体の変化、育児への不安、環境の変化によって引き起こしたものだと考えられています。
よくみられる精神症状として、イライラ、悲しみ、気分の変動、不安、無力感、絶望感、怒り、疲労感、睡眠障害などがあります。よくみられる身体症状として、疲れやすい、体力が落ちた、胃腸のトラブル、頭痛、腰痛、下腹部の痛み、関節痛、めまい、尿失禁、髪の毛が抜ける、便秘、肌荒れなどがあります。ほとんどは出産1ヶ月以内に発症します。
中医学の考え方では、出産後の女性の体は気血不足しがちで、その影響を受けて肝の巡りの停滞、血の流れの滞りもなりやすいです。産後の女性に多くみられる心身の不調は、それらの誘因によるものだと考えられます。誘因が元々の体質と絡み合い、より複雑な症状が現れてきます。
中医学の対処方法は、エネルギーと栄養である気血を補うと同時に、肝の気の巡りを良くし、血行を促進して滞っている古い血を解消していきます。そのうえ、体質に応じて体質改善も行うため、不調の改善が期待できます。
×
メンタルのお悩み

「気になりだしたら止まらない」
「取り越し苦労だとよく言われる」
「考え出すとどんどん嫌な考えになって来て……」
「不安な感じがしてくるとどうにも落ち着かないんです」
ひとに話しても、なかなか分かってもらえない。ご来店されるお客さまは、みなさま口々にそうおっしゃいます。
確かに経験したことがないと、実感しにくい不調かも知れません。
でも一度経験した人間には、痛いほどこのツライ気持ち、よく分かります。
さて、中医学では、こうした不安は「心」の病態だと考えています。
心臓の「心」ですね。
考えたり眠ったりといった人間のこころの機能は「心」のグループの働きだと考えてお手当します。
ここの臓器に足りないものがあるか、逆に何かが邪魔しているか……
それを分析して、あなたに合ったお手当を。
漢方薬を正しく選ぶと、着実に、おラクになってくるのが実感出来ます!
×
アレルギーのお悩み
アレルギー反応=免疫の乱れ……みなさまよ~くご存じですね。
漢方は免疫疾患によく効きます。これもみなさまよくご存じのことと思います。
では、季節をいち早くお知らせしてくれる、ツラ~イ鼻炎は、どう治していくのでしょう。
「中医学」では、いくつかの臓器が協調して免疫の働きをコントロールしていると考えます。そこの弱点を克服するのがまずひとつ。
そして、症状を起こしている現場の状態を調整します。
「ハナミズがあふれる」……ハナミズの材料=余計な水分の供給を絶つ
「息ができない」 ……呼吸=「気」を巡らせる
「目が痒い」 ……「目」に入る経絡の熱を解除
etc.etc……
発症の引き金になる原因物質が「花粉」であれ「ダニ」であれ、「気温の変化」でも「日内変動」でも、「その症状が起こる体内の原因」がなくなれば、誰でも快適な毎日を送ることが出来ます。
お悩みの方……どうぞ一度ご相談くださいませ。
×
胃腸のお悩み
繰り返す痛み。
こみ上げるゲップと不快感。
背中にまで達する苦しさ。
これは経験したひとにしか分からない苦しさですよね。
最もツライのは、再発すること。
胃潰瘍になってしまう状況が再現すると、この病気は、すぐ首をもたげます。
内服薬の登場で、以前のように手術の必要はなくなりました。
しかし、「胃酸を抑える」くすりでは、再発は防げません。
というよりも、「そのくすりをのむのを止めれば」すぐに再発してしまうようになることも。
くすりで抑えていた胃酸が、くすりを止めるとより多く分泌されるようになるからです。
いわゆる「リバウンド現象」です。
中医学(=漢方の理論)では、こうした胃痛の原因を、大きく二つの働きのバランスから考えます。
ひとつには、「脾胃」の問題。
胃腸が弱ければ傷つきやすい。ちょっとした刺激で痛みが起きてしまいます。
もうひとつは「肝」の問題。
分かりやすい言葉でいうと、「ストレス」です。
ストレスが身体の調節機能を乱し、他臓に悪影響を与えるのです。
このふたつのどちらが主となって引き起こされた潰瘍かそのバランスを回復するにはどうすればよいか。
再発の繰り返しから脱出するには、そこを調整しなければ
なりません。
丈夫な胃を、作り治しませんか?
×
泌尿器のお悩み

漢方の面目躍如!!
いくつかのメーカーさんの積極的な広告のおかげで、「漢方薬があるんだ!」と広く知れ渡るようになりましたね。
よろこばしいことです(^o^)。
しかし。
夜、寝ているときにトイレに行きたくなる。
それにはいくつかのパターンがあります。主なところでは…
1. 昼と夜で、おしっこをつくるスイッチが切り替わらなくなり、夜なのに昼と同じペースで尿が作られ続ける。目が覚めてトイレに行くとそれなりの量が出る。
2. 眠りが浅いため、おしっこはそんなに溜まっていないのに、気になってトイレに行きたくなる。 寝返りを打っているうちに行きたくなる場合も。
3. 明け方早く目が覚めて、「まだゆっくり寝ていたい」のにもう眠れない。トイレにも行きたいような気がして…
4〔番外編〕. ものごとが気になりだすと止まらない。「行きたくなったときにトイレが見つからなかったらどうしよう」と思うと、いてもたってもいられずトイレに飛び込んでしまう。慣れていないところへの外出時に特に困る。
ひとくちに「夜間尿」とくくるのには、ちょっと無理がありますね。
中医学的にいっても、それぞれのパターンは別の病態と判断しています。当然改善法も違ってきます。
×
全身のお悩み
- どうして起こるのか
- どこにどんな乱れがあるのか
- どうすればそれを調整できるのか
×
耳鼻のお悩み
×